目的 9コマ分の「本時の指導案」を一気に作る
前回「数学の単元計画づくり」で5単元の計画を作成しました。
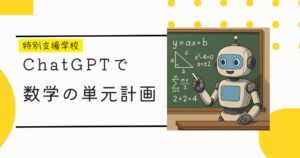
各単元はそれぞれ9コマの授業で構成されています。
前回は9コマの内容まで作りました。
 いち関係者の私
いち関係者の私次はそれぞれの「本時の指導案」です。
前回のカスタムGPTをそのまま使う
本時の指導案を作成するには、単元をどのように作ったかをChatGPTが覚えている必要があります。



前回の単元を作ったカスタムGPTをブックマークしておいたものを使えばいいですね。
プロンプトは「『数と計算1』の1コマ目の指導案を提案してください」だけ
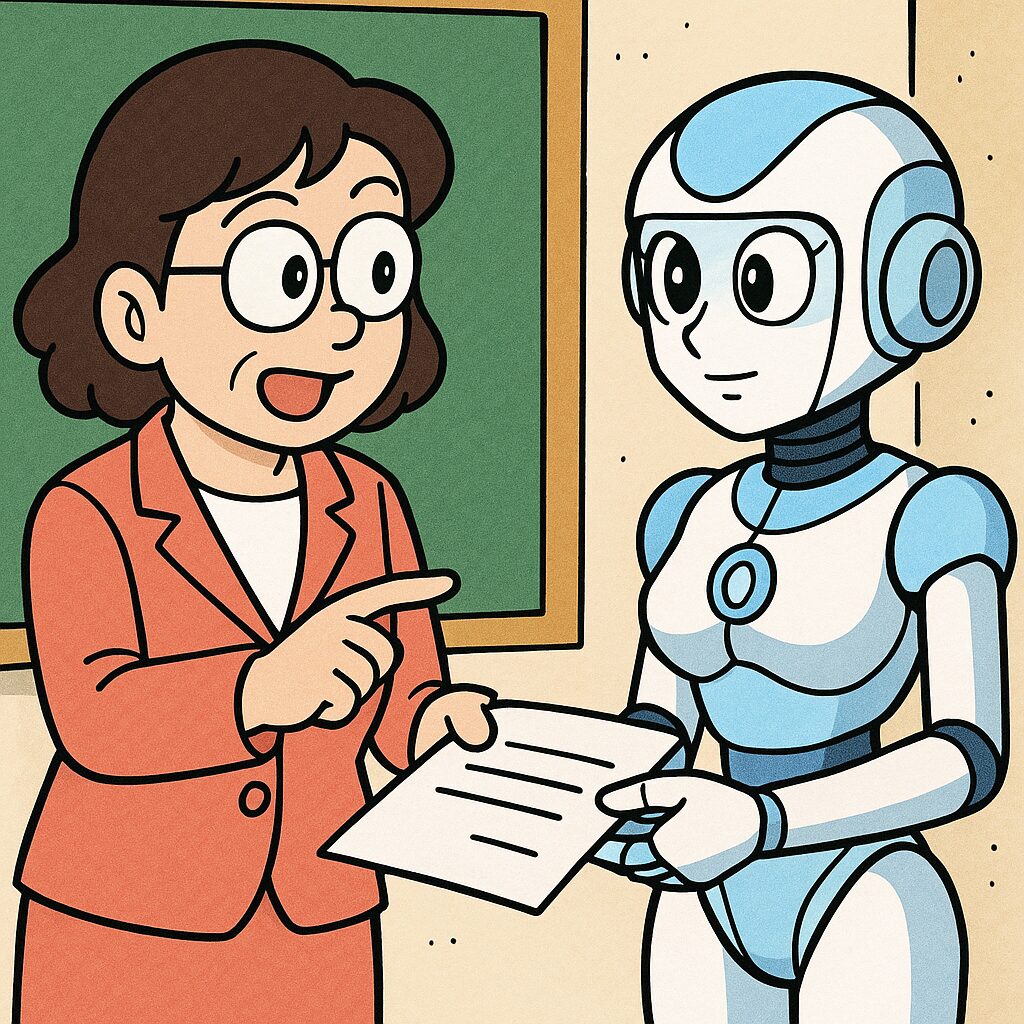
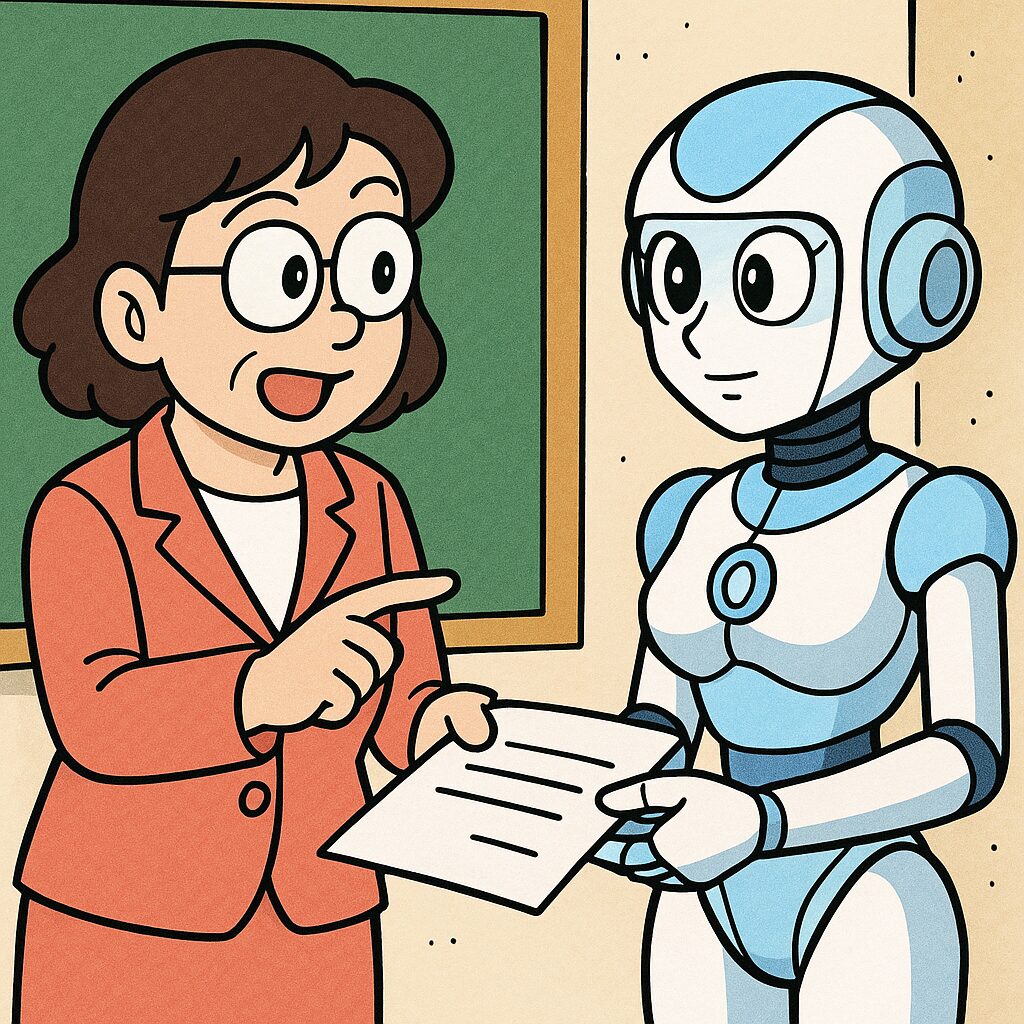
ChatGPTは同じチャットならそれまでのやり取りの情報が記憶されていますので、こんな大雑把な命令ができるわけです。
また、Knowledgeとして教科書そのものが入っていることもポイントでしょう。



「数と計算1」の1コマ目の指導案を提案してください。



承知しました!
それでは「数と計算1」単元の**1コマ目:『大きい数の読み方・書き方』(P.6)**に対応する授業案を、特別支援学校・中学部1段階の生徒向けに、楽しく・生活に役立つ・30分構成でご提案いたします。
📘 指導案(30分)
単元名:「数と計算1」 コマ1/9
題材名:大きい数の読み方・書き方(P.6)
🏁 本時の目標(ねらい)
- 「万・億・兆」といった大きい数の読み方や、桁のまとまり(コンマの使い方)を知る
- お金やニュースなど、身の回りの中で大きい数を見つけてみようとする
📌 評価規準(本時における視点)
- 【知・技】「万・億・兆」の意味を理解し、簡単な読み書きができる
- 【主】活動に楽しんで参加し、身の回りにある数に興味をもとうとしている
⏱ 時間配分と展開
| 時間 | 展開 | 活動の概要 | 指導上の配慮 | 教具・教材 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 導入 | 実際の値札カードや電化製品の広告を提示。「いくらだと思う?」クイズで興味づけ | 知っている数とのギャップに驚かせる | 値札カード、大判チラシ |
| 5分 | 展開① | 教科書P.6の事例から「万・億」の読み方確認。数字を板書し、声に出して読む | 3桁ごとに区切ることで桁のまとまりを意識 | 数カード、ホワイトボード |
| 10分 | 展開② | 数字カードを組み合わせて、先生が金額を出題。「いくらと読む?」クイズ形式で練習 | 読みづらい生徒にはヒントカードを配布 | 数字カード、ヒント表 |
| 5分 | 展開③ | 実生活で出てくる大きい数を紹介(例:家の価格、国家予算、電気代の年間額など) | 興味に応じて職業や家族の話題とつなげる | スライドまたは図カード |
| 5分 | まとめ・振り返り | 「今日覚えた数で、いちばん大きいのはどれ?」発表&振り返り | 桁が多くても「区切って読む」安心感を意識 | ミニカード、振り返りシート |
✨ 活動の工夫ポイント
- 大きな数字にワクワクさせる!:現実感のある「1億円の札束写真」などでインパクト◎
- 読むだけでなく言ってみる!:言葉に出して「万」「億」を体に覚えさせる
- スモールステップで:数字の「,(コンマ)」=“読んで区切る目印”として視覚的に支援
と上記のように出力してくれました。



2コマ目もお願いします



ありがとうございます!
それでは「数と計算1」単元の**2コマ目:『大きい数の比較』(P.7)**に対応した指導案をご提案します。
📘 指導案(30分)
単元名:「数と計算1」 コマ2/9
題材名:大きい数の比較(P.7)
🏁 本時の目標(ねらい)
- 数字の桁の違いや位の違いに気づき、「どちらが大きいか」を見分けることができる
- 実際の買い物や給料、賞金などを例に、大きい数の大小を判断する力を養う
📌 評価規準(本時における視点)
- 【知・技】大きい数の大小を比較し、正しく「どちらが大きいか」を言える
- 【思・判・表】数字の並びから、自分で大きさを比べようとする
- 【主】ゲームや活動に楽しんで参加し、数字に親しもうとする
⏱ 時間配分と展開
| 時間 | 展開 | 活動の概要 | 指導上の配慮 | 教具・教材 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 導入 | 前回の復習をクイズ形式で。「1億円ってどれくらい?」「数字を声に出して読もう」 | 知っている金額を出して比較すると◎ | 数カード、札束写真 |
| 5分 | 展開① | 教科書P.7の例を使って、数字を左右に並べてどちらが大きいかを判断する | 桁のそろえ方を視覚的に見せる | ホワイトボード、数字マグネット |
| 10分 | 展開② | 「どっちが大きい!?カードゲーム」対戦形式で大小を比べる | 数が苦手な生徒は「1桁ずつ確認」支援 | 比較カード、順位表 |
| 5分 | 展開③ | 実生活例で比較:「コンビニの売上vsスーパー」「1万円札と100円玉100枚」など | 桁数が同じでも“上位の位”を見ることに気づかせる | チラシ、金額カード |
| 5分 | まとめ・振り返り | 今日の一番大きかった数は?「わたしのびっくりナンバー」発表 | 自分の好きなものと数字を結びつけて発言促進 | 発表カード、振り返りシート |
✨ 活動の工夫ポイント
- ゲーム性を活かして判断力を育てる:「比較ゲーム」で自然に数に触れる
- 具体物・金額との結びつけ:「現実にあるお金」で桁の差を実感
- 「なぜ大きいのか?」を言えるよう支援:自分の言葉で説明する力を養う機会に
「1億円ってどれくらい?」が具体的にわからなかったので、



「1億円ってどれくらい?」の具体的なやり方を教えて
と聞きました。
すると



とても良い質問です!
「1億円ってどれくらい?」は、生徒たちに大きい数のスケール感を“体で感じさせる”導入として非常に効果的です。特別支援学校での指導においても、視覚・触覚・驚きを活かすことで、数字への興味を高められます。以下に、30分授業の中で使える「1億円ってどれくらい?」の**具体的なやり方(5〜7分)**をご紹介します。
💰 体感活動「1億円ってどれくらい?」
🎯 ねらい:
- 「億」という大きい数のスケールを、数量ではなく量感・重さ・空間で実感させる
- 数の桁(0の数)と金額の感覚を一致させる
🧰 準備物:
- 模擬1万円札(カラーコピー)×100枚(=100万円)
- それを束ねた「100万円の札束」×10(=1,000万円)
- それを10束そろえて「1億円」の模型(ダンボール箱などにまとめる)
- 1億円の重さのイメージ:本物なら約10kg。砂や新聞紙を詰めてそれに近づけると◎
🪄 活動手順(約5〜7分)
| ステップ | 内容 | 指導のヒント |
|---|---|---|
| ① 導入クイズ | 「1億円って、1円玉で何枚分?」「1万円札で何枚?」 | 黒板やスライドに提示。「100万円」「1,000万円」も出しておく |
| ② 模擬1万円札で100万円の札束を見せる | 「これが100万円。思ったより小さい?大きい?」 | A4サイズにピッタリ収まる札束にする。紙の厚みは少し出しておく |
| ③ 札束10個で1,000万円! | 10個積んで「1,000万円」出現 | 教卓などにずらっと並べるとインパクト◎ |
| ④ 1億円(=札束100個分)登場! | ダンボール箱やかばんに詰めて「どーん!」と出す | 「これ、持てる?」「運べる?」など話を振ると盛り上がる |
| ⑤ 感想タイム | 「こんなにあると何が買える?」「どうやって数える?」 | 「数字」→「想像」→「実感」へつなげる時間に |
📝 プラスワン:視覚化ポスター
- A3やA2用紙で「1万円札1枚」「100万円=札束」「1億円=10kg」などの比較図ポスターを掲示
- 「1億円で買えるものリスト」(例:高級車、家、宝くじ100万枚!)なども話題に◎
🌟 指導上のポイント
- 数の苦手な生徒には「0が8個あるよ」「100万円が10個で1,000万円!」と視覚言語で分かりやすく
- 驚き・楽しさを優先してOK。「すごい!」「持ってみたい!」で関心を引き出せれば大成功!
と答えてくれました。
実際にできるかどうかはちょっと疑問が残る取り組みでしたが、十分参考にはなります。
このあとも



「どっちが大きい!?カードゲーム」対戦形式で大小を比べる のやり方を具体的に教えて
と入力して回答をもらい、その他の教材について3回程度やり取りをしたあと



ありがとうございます。では、次に3コマ目の「分数の意味の理解」に対応した指導案をお願いします
と次の指導案を出してもらいました。
その後は教材についての疑問はあまりなかったので、サクサクと9コマ分を作成しました。



出来上がったものはまたダウンロードできますよね。



こちらになります。「数と計算1」 各コマごとの指導案
もちろん修正して使用する


上記の出来上がったファイルの指導案はもちろんそのままは使いません。
あくまでも「たたき台」です。
さらに、単元を一人で担当するわけではありません。
3人で担当しますので、上記の指導案を渡したら、あとはその先生にお任せとなります。
さらに進み具合をみて、「もう少し個々に時間をとったほうがいい」と考えた場合には次のコマまで延長になります。
そのへんは柔軟に対応していきます。



特別支援学校は個別の指導が基本ですから、普通学校のようにな「◯時間で全て終える」というノルマがありませんので、上記のようなことが可能になります。
まとめ
- 前回、単元の大まかな目標と内容が9コマ分出揃っているので、今回は単元の「本時の指導案」を9コマ分一気に作ることができる。
- 前回とおなじChatを使うことで、ChatGPTが覚えているので効率よく作ることができる。
- カスタムGPTであるが、基本的にChatGPTなので、途中でわからないことについては相談することができる。
- いつもそうだが、ChatGPTで100%は求めない。「たたき台」として使用する。
- 出力されたものはワードなどで加工したり、担当の先生にお渡しして作り直してもらう。

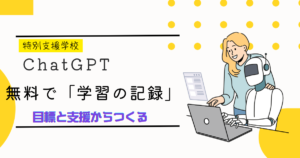
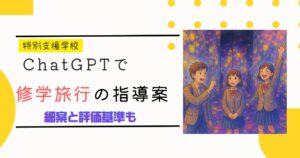


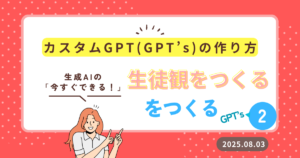
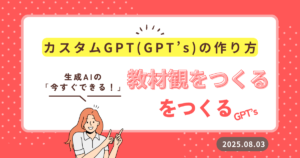
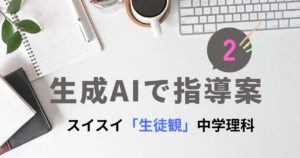
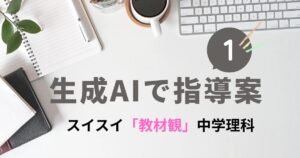
コメント