もう一度確認します。
指導案を生成Aiに作らせることは「楽をすること」ではありません。
です。
- 今回の私が作成したカスタムGPTの場合、質問に真摯に答えていくこと。
- 出来上がったものを十分に精査・推敲すること。
- そして、出来上がった文章をよく読み「自分の現在のポジション」を理解すること。
1が大事なのは当然です。
しかし、2と3に時間をかけて「自分との対話」をすることが「苦労・努力のポイントを高次元に引き上げること」です。
 いち関係者の私
いち関係者の私私はそう思うのですが、皆さんいかがですか?
3についてはちょっと分かりづらいかもしれません。
文章に表して始めて「自分が考えていることを自分で気づく」ということです。
これは意外によくあります。
生成Aiを使った場合、自分より上の次元の文章が出力されてしまうこともあるでしょう。
しかし、それはそれで、自分で気づくものです。
それはさておき、今回は「教材観」「生徒観」「指導観」の作成を通じて「生成Aiを使う意味」を考えます。
「教材観」「生徒観」「指導観」全部並べてみた
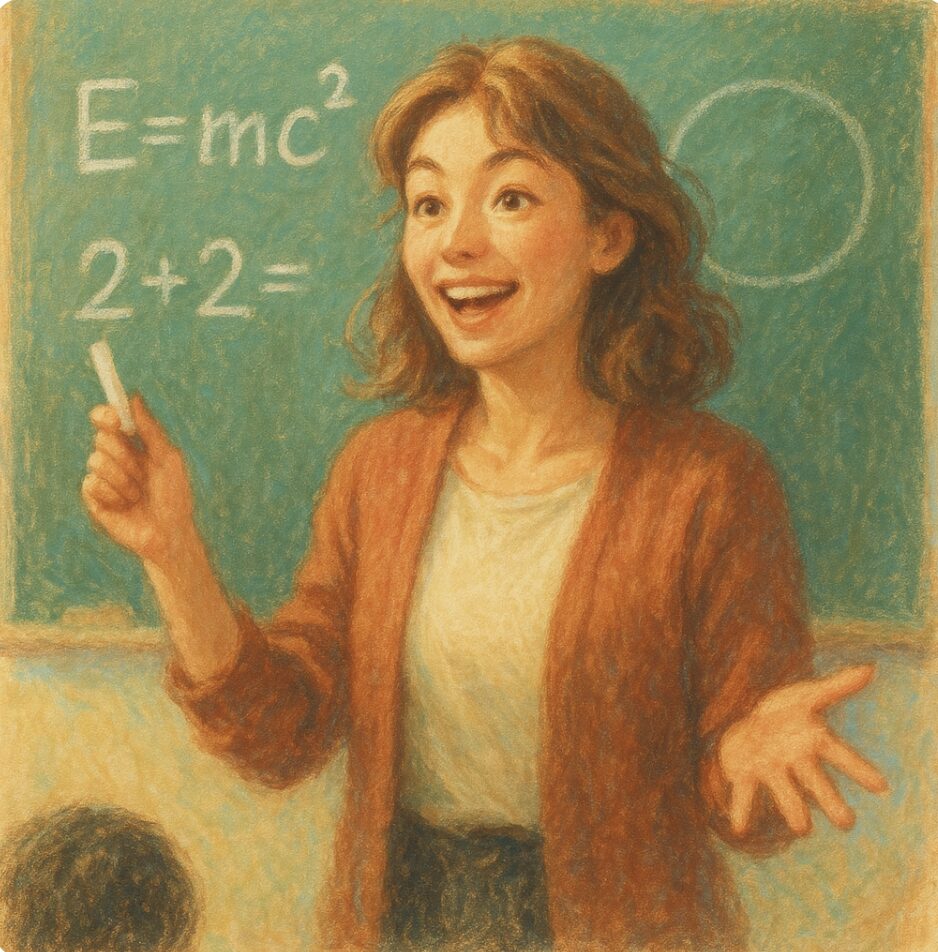
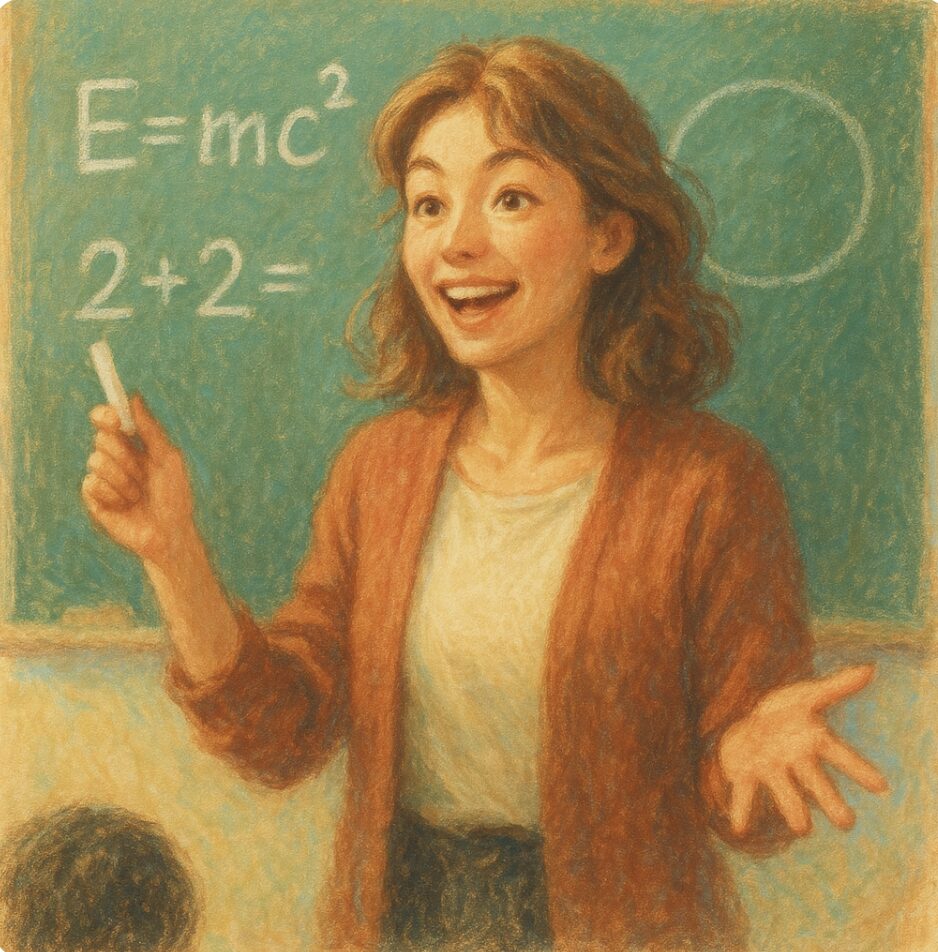
今回作成したカスタムGPTでつくった「教材観」「生徒観」「指導観」を並べてみました。



ChatGPTに頼んですべてダミーで作ってあるので、ご了承ください。
教材観
この単元では、化学反応という目に見える現象を通して、その背後にある原子や分子の世界を理解させることをねらいとする。生徒は、鉄やろうそくといった身近な物質が変化する様子を観察する中で、「なぜ変わるのか」「何が起きているのか」と問いをもち、自ら仮説を立てて検証する過程を重ねることで、論理的に考察する力を育んでいく。ごみの焼却やCO₂排出といった環境問題との関連も扱い、化学変化が日常生活や社会と深く関係していることに気づかせたい。また、実験での気づきを起点に、生徒同士の対話や予想・検証を通して理解を深める探究的な授業を大切にしたい。
この単元を通して、生徒が目に見えないミクロの世界を科学的に捉える視点を獲得し、科学的思考力を育てることを目指す。その中で「考える理科」の基礎を築き、論理的に世界を理解しようとする姿勢を身につけさせたい。
生徒観
この単元では、化学反応という具体的な現象を出発点に、目に見えない原子・分子の世界を理解させることがねらいとされている。対象となる中学2年生は、論理的思考が発達途上であり、実験や観察などの体験的活動を通して概念理解を深めることが効果的である。
学級は落ち着いた雰囲気をもち、協力的に活動する力がある一方で、対話を通じて考えを深め合う経験はまだ多くない。実験には興味をもち前向きに取り組むが、結果や正解を重視する傾向が強く、考察や仮説の構築には課題が見られる。化学変化に関する日常的な経験はあるものの、それを理科的に捉える視点は未発達であり、生活や社会との関連づけを通じた視野の広がりが期待される。
今後の授業では、生徒の好奇心を活かしながら、科学的な問いを立て、それに向かって思考を深めていく力を育成することが求められる。
指導観
本授業では、化学変化という目に見える現象を出発点に、目に見えない原子や分子の世界を科学的に捉える力を育成したいと考える。生徒が実験で出会う現象に対して「なぜそうなるのか」と問いをもち、自ら仮説を立てて検証し、論理的に考察していく過程を重視する。そのために、生徒の好奇心を引き出す問いかけや、仲間との対話による思考の深まりを大切にし、学びの中で生徒が主体性をもって探究する姿勢を育む授業を目指す。
また、単なる現象の観察にとどまらず、実験を起点とした対話やICTを活用した視覚的な支援を通して、生徒の思考の可視化と理解の深化を図る。化学変化と社会・生活との関係を意識させることで、理科の学びが現実世界とつながっていることに気づかせ、科学的に世界を見る視点の獲得を促したい。教師としては、生徒一人ひとりの問いに寄り添い、ともに学ぶ伴走者としての姿勢を大切にしながら、思考と対話を中心に据えた「考える理科」の実現をめざす。



ちょっと教材観が生徒観に近くなってない?
そうなんです。
教材観を修正する
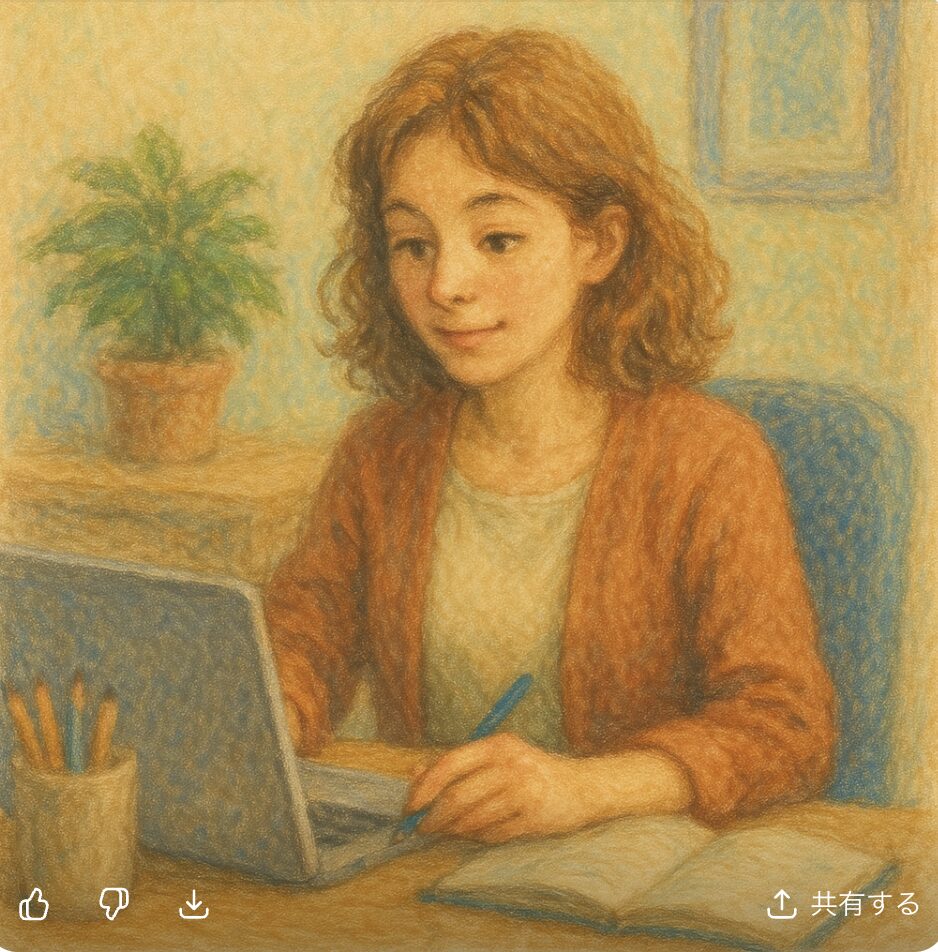
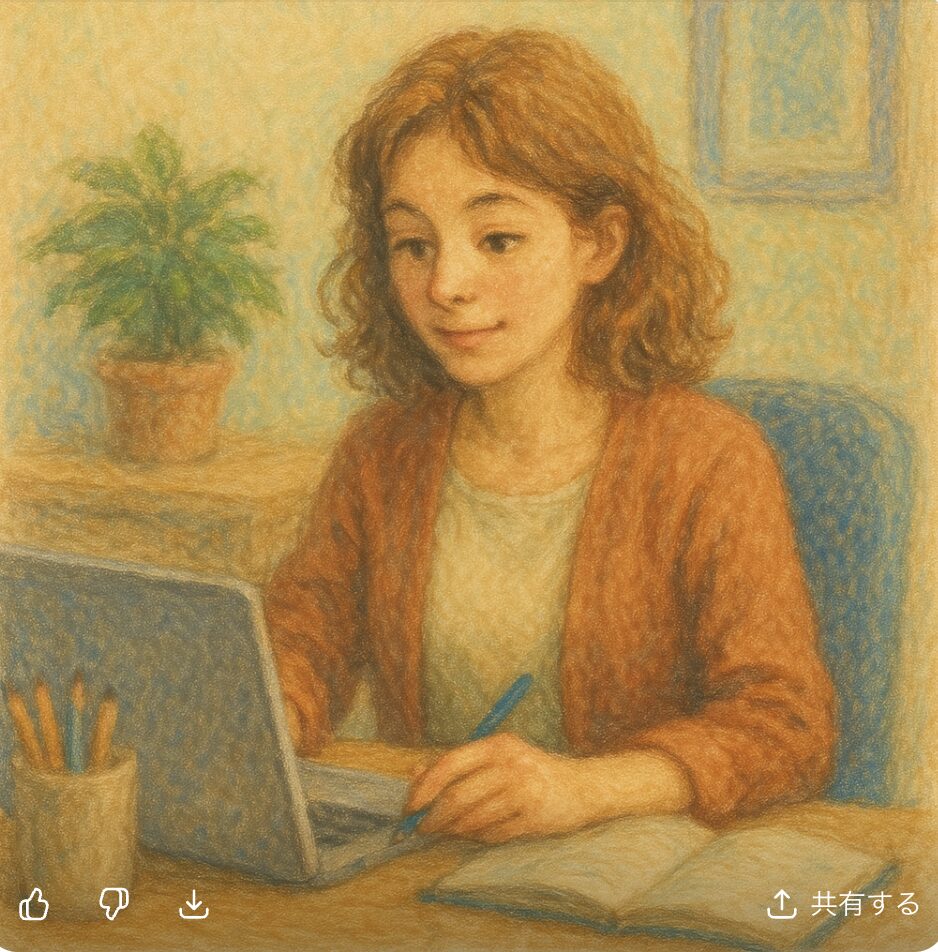
こうして並べてみると、教材観に「教師の思い」が入り過ぎのようです。
「子ども観」が教材観に入るとはいえ、ちょっと多すぎます。
そこで、そのチャットを呼び出して



後半に教師の指導の方針が多いようです。化学変化と原子分子の教材についてもう少し分析したものを掲載してください
教材観の修正版
「化学変化と原子・分子」は、物質の変化を macroscopic(巨視的)な視点から捉えるだけでなく、その変化の本質を microscopic(微視的)に理解することを可能にする教材である。例えば、質量保存の法則や化学反応式の導入を通じて、見た目の変化だけでなく、物質を構成する原子の種類や数に着目しながら変化の規則性を捉えることができる。これは、理科の中核概念の一つである「構成と変化」に深く関わっており、自然界の多様な現象を原子・分子レベルで説明する基盤となる。中学校理科において、物質の本質を扱うこの単元は、科学的世界観の育成において極めて重要な位置を占める。
この単元を通して、生徒が目に見えないミクロの世界を科学的に捉える視点を獲得し、科学的思考力を育てることを目指す。その中で「考える理科」の基礎を築き、論理的に世界を理解しようとする姿勢を身につけさせたい。
結構いい感じになったと思います。



私の感覚では、です。
一番最初も述べましたが、自分で指導案を作成する場合、ここからが大事です。
できた文章を精査・推敲する
特に「指導観」は十分に検討すべきでしょう。



できからいいや!
ではダメなわけです。
それをしてしまうと、生成Aiを使って楽をするだけ、中身のない文章が出来上がってしまうのです。
ここまでの「0→1」を時短できた分、ここからの推敲に時間をかけることで、
苦労・努力をするポイントを高次元に引き上げること
が実現するのです。
精査・推敲し始めると調べたくなる
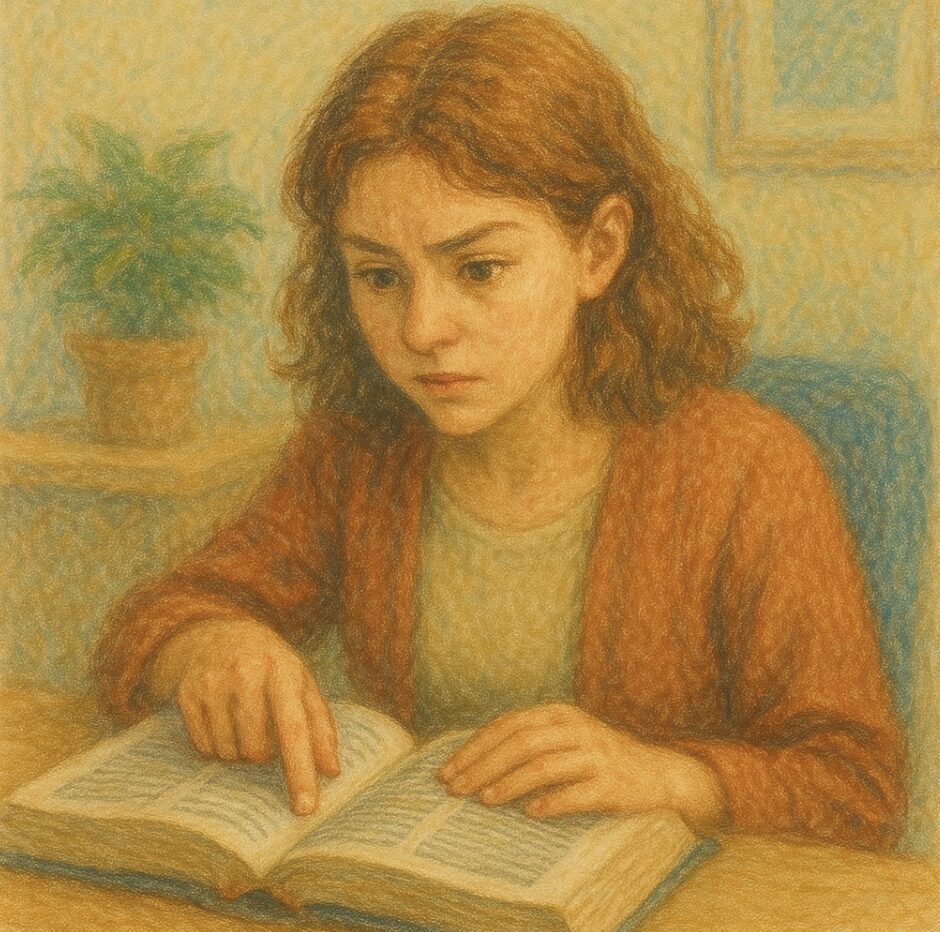
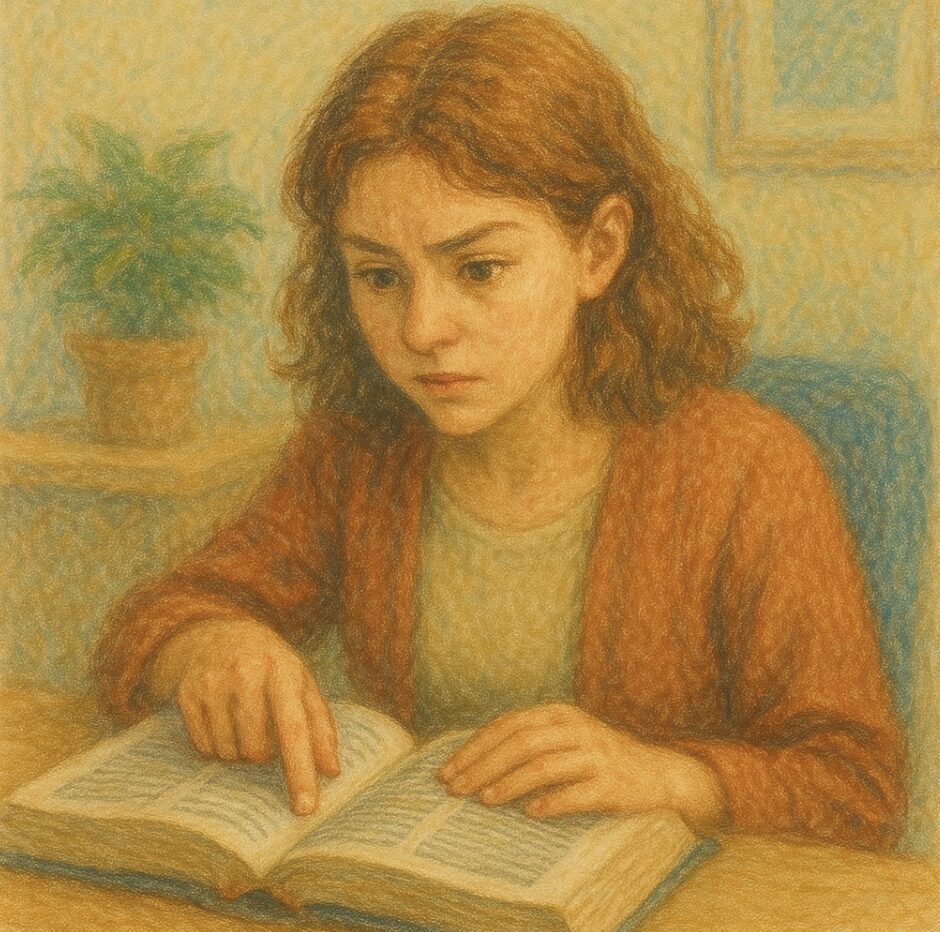
文章を正確に書こうとすれば、当然調べたくなります。
表現が正しいのか、指導要領ではなんと書いてあるのか、いろいろ気になってきます。
そんなとき活躍するのもAIです。
NotebookLMなどを使えば、指導要領の内容は簡単に検索できます。
すると、理解が深まります。
これは
AIは100点を取るための道具ではなく、200点を取る道具
と言われる一例だと思います。



より深く、より高次元で理解できるわけですね。
みんな「いい仕事をしたい」


うちの職場でも、「業務削減」が叫ばれています。
たしかに重要でしょう。
本当に削減してほしいものは山程あります。
しかし、真っ当な教員であれば、とくに若い方ならば
「いい仕事がしたい」
の方が先にくると思います。
そのためには時間を使って、残業してでも仕事をするでしょう。



研究授業があれば、良い授業、良い指導案を書いて評価されたいと誰しもが思うのではないでしょうか。
その人たちが生成Aiを使用したからと言って「生成Aiが出してくれた文章をそのまま使う」という適当な仕事をするでしょうか?



するはずないでしょ!
と思うのです。
「生成Aiを使っていい仕事をしようとする」
のではないでしょうか?
生成Aiはサボりの道具!? いいえ。
その側面はあるでしょう。
しかし、正確な表現で言えば
生成Aiは「効率化」の道具です。



私から言わせれば「業務削減の切り札」とも言えます。
指導案で言えば、研究授業などの勝負をかけた指導案は十分に精査・推敲・熟考すべきでしょう。
しかし、その他のものは「Aiにお任せ」でもいいのです。
その分、生徒と触れ合う時間を、本当に心を砕かなければならないところ、に時間をかけるべきです。
これまでは「指導案をなにかに任せる」などということは夢のようなことでした。
しかし、生成Aiならできます。
正しい使い方を知っていれば、時間をかけて自分の分身のようにカスタマイズすることも可能でしょう。
「生成Aiを普通に使う」新採
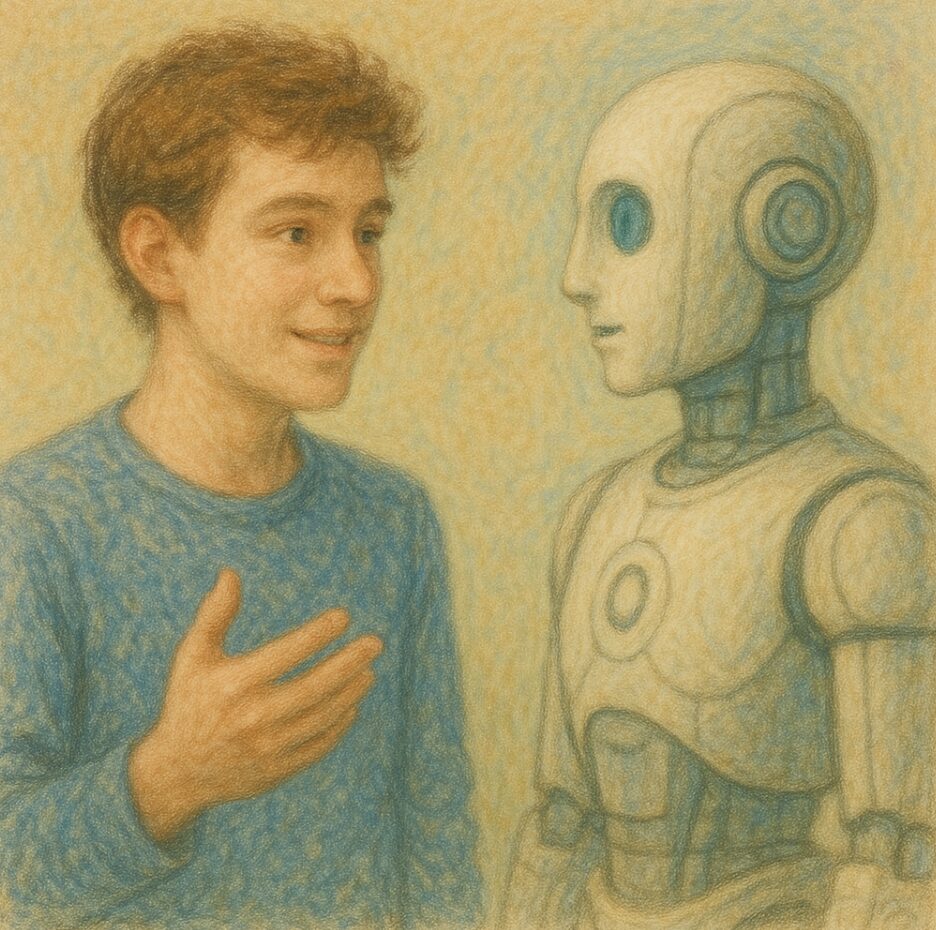
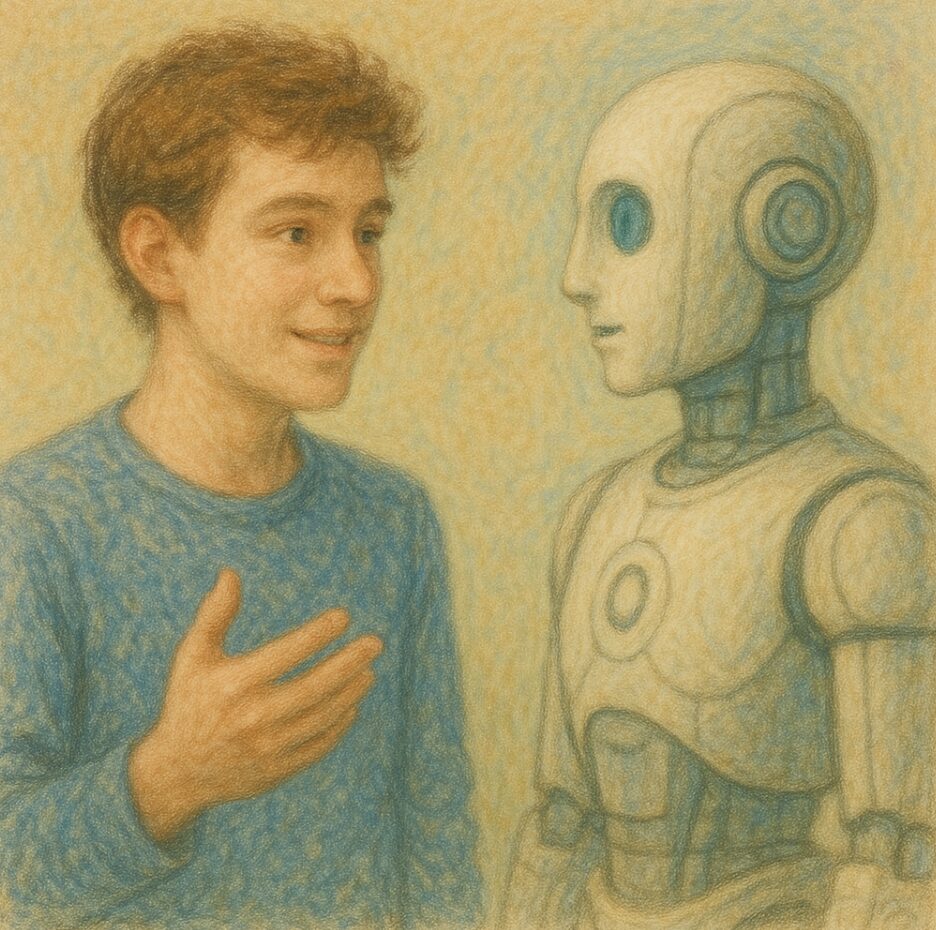
かつてワードやエクセルを当然のように使える新人が職場に入ってきたことと同じく、早ければ来年2026年度からは生成Aiを普通に使える新人が現場に入ってくるでしょう。



大学で指導案は生成Aiに書かせました。
と、しれっと言う新人がきっといるでしょう。
そのとき、職場は、現場の私達はどのように反応すればいいのでしょうか。



皆さんはどう考えますか?
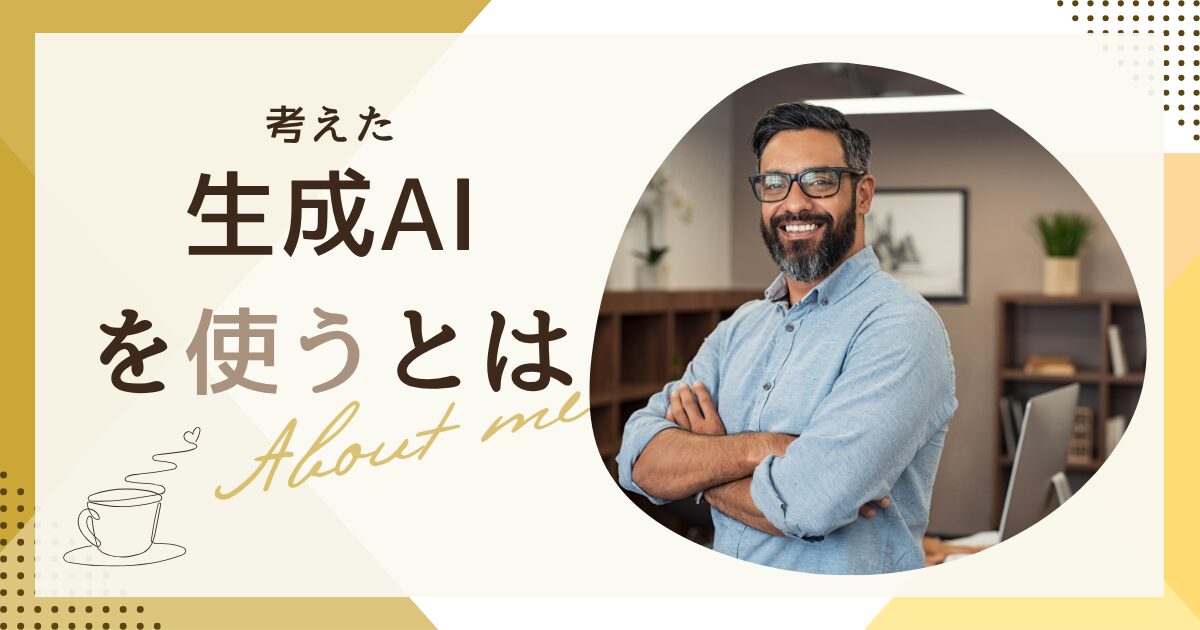

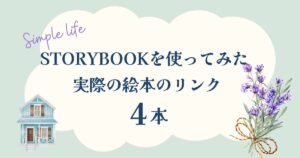
コメント